
導通チェッカーの実験

| 導通チェッカーは、導体と不導体、ケーブルの導通・断線チェックなどに使います。 仕組みは、回路の一部を切り、チェックする物を間に入れて、その導通で回路を完成させ、ランプやLEDを点灯させたり、ブザーを鳴らす事で導通を確認するものです。 調べる物によっては、電圧や電流の余り加えられない物もあり、用途を考えて使う必要があります。 ここでは、電源は3V共通で、豆電球やLED、ブザーなどを電源にそのままつないだ簡単な導通テスターと、トランジスタを利用した場合の比較を行います。 |
☆準備☆
 |
☆材料☆ トランジスタ 2SC−1815Y 2SD−880Y LED(高輝度) 豆電球 豆電球ソケット(加工済み電池スナップを参考に加工して下さい。) 収縮チューブ 単3乾電池x2 電池ソケット(単3乾電池x2用) 加工済み電池スナップ ミニブレッドボード ジャンプワイヤ・セット |
 |
☆道具☆ 半田コテ コテ台 半田 ニッパ ピンセット テスター テストリード(先がみの虫クリップ) |
| 導通チェッカー1(豆電球を直接電池につないだ場合) 豆電球と電池(3V)だけのシンプルな導通チェッカーです。 テスト端子をショートさせると、電流が250mA流れました。 |
|
 |
 |
| 導通チェッカー2(LEDと抵抗を直接電池につないだ場合) LEDと抵抗、電池(3V)だけのシンプルな導通チェッカーです。 テスト端子をショートさせると、電流が11mA流れました。 |
|
 |
 |
| 導通チェッカー3(ブザーを直接電池につないだ場合) ブザーと電池(3V)だけのシンプルな導通チェッカーです。 テスト端子をショートさせると、電流が4mA流れました。 |
|
 |
 |

| 導通チェッカー4(豆電球・トランジスタで増幅した場合) 豆電球に流す電流が250mAとやや大きいのでトランジスタも 少し大きめの2SD−880Yを使いました。 抵抗1kΩベース電流は約2mAでした。 |
|
 |
 |
| 導通チェッカー5(LED・トランジスタで増幅した場合) トランジスタは2SC−1815Yを使いました。 抵抗10kΩでベース電流は約300uAでした。 (抵抗R1を100kΩにしても点灯しましたが、少し暗くなりました。 |
|
 |
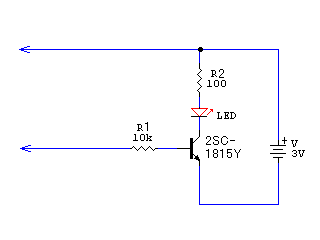 |
| 導通チェッカー6(ブザー・トランジスタで増幅した場合) トランジスタは2SC−1815Yを使いました。 抵抗10kΩでベース電流は約300uAでした。 |
|
 |
 |